スペガ通信
シャラとヒメシャラ
2015年10月24日
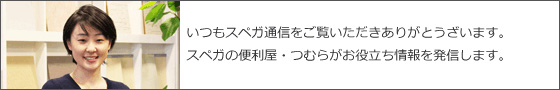
こんにちは![]()
スペガ通信をお読みいただきありがとうございます![]()
今回のテーマは「シャラとヒメシャラ」です。
平家物語の冒頭に
「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響き有り 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす」
とあります。
シャラノキは仏教で聖木とされる沙羅双樹(さらそうじゅ)にちなんだ名前ですが、
インド原産のシャラの樹とナツツバキは別物です。
平安時代の古い昔から、庭木として親しまれているナツツバキが、
現在も庭のシンボルツリーとして人気が衰えていません。
その魅力のポイントは樹姿や幹だと思います。
樹形は直立して、やや上向きに枝を広げるため、
ヤマボウシと違い、横幅をとりません。
自然樹形ですらっとした樹姿です。
ある程度大きく育つと幹の皮がめくれ、美しい模様が見られます。
皮が落ちた跡は、赤褐色になり、サルスベリやリョウブの木肌に似ています。

シャラノキ

ヒメシャラ
※ヒメシャラとシャラノキの違い
ヒメシャラの花はシャラノキより小ぶりです。
またヒメシャラの木肌はシャラノキより赤みがかっています。
ヒメシャラのほうが生長が遅いです。
それではスペガ通信を最後まで読んでくださり、ありがとうございます![]()
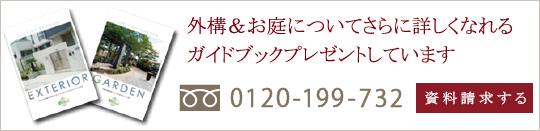
18:00 | [◎シンボルツリー(落葉樹編)]
 【千葉・埼玉】お庭・外構のデザイン設計・施工・管理専門店
【千葉・埼玉】お庭・外構のデザイン設計・施工・管理専門店

